「〜すべき」ではない、仮定法現在のshouldとは
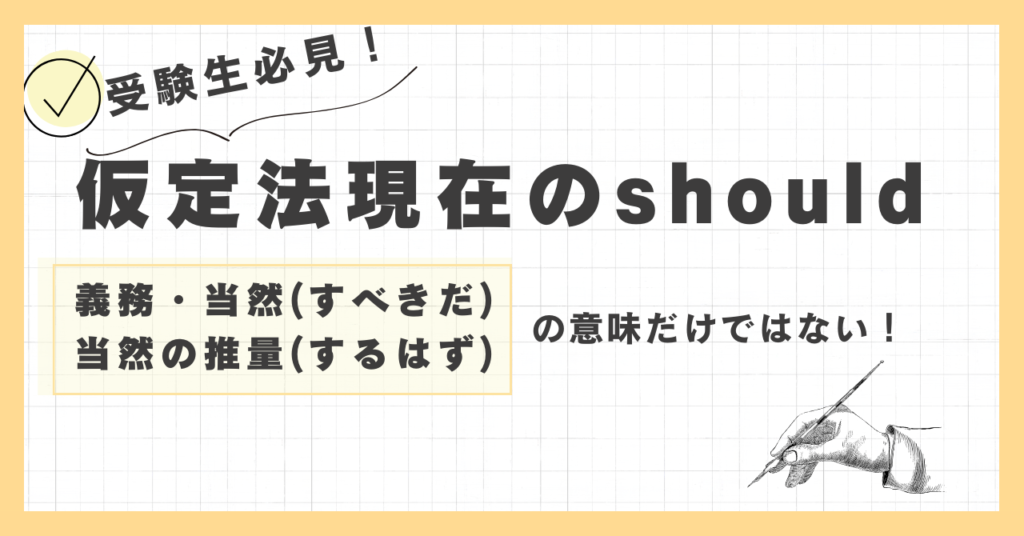
大学入試問題頻出の仮定法のshouldについて解説します。
I came back home before 9 pm for fear that my father ( )angry.
①got ② to get ③should get ④getting
解答は③のshould getになります。
I came back home before 9 pm for fear that my father (should get )angry.
「私は父が怒ることを恐れて、21時前に家に帰った。」
for fear that (sv〜)は、(svすること)を恐れて
主節では過去形が使われているのに、shouldを使うのでしょうか。解説していきます。
結局のところ、何を表しているshouldなのか?
I suggest that you should study English.
私はあなたが英語を勉強することを提案します。
「勉強した方がいいよ、勉強しなさいよ」という文ですね。
この文を発言した際に、「あなたが勉強する」という状況はまだ起こっていません。
つまり、まだ起こっていない、現実になっていないことを表すshouldなのです。
Suggestで提案するという意味だから、このshouldは「〜すべき」の意味となるのは間違いです。
仮定法現在のshouldなので、普通の助動詞のshould(義務、当然、当然の推量)とは異なります。
仮定法現在とは、仮定法現在は現在または未来の不確実な仮定を表す。条件文で仮定法現在が使われるのは、いまでは慣用的な表現か、擬古体の文や格調を重んじる文を除いてはまれで、代わりに直説法現在が使われる
ロイヤル英文法
仮定法現在のshouldが使われる場所
- 要求、提案、必要を表す「動詞」のthat節の中
- 【動詞】demand(求める、要求する), request(依頼する、要請する), suggest(提案する), propose(提案する), advise (忠告する)など
- 形容詞のthat節の中
- essential(不可欠な), necessary(必要な), vital(必要不可欠な)strange(奇妙な)など
入試問題で頻出です。しかもこれはNEXT STAGEやVintageには解説されていないのです。
(問題ではたくさん出てきますが仮定法現在という言葉で説明されていません)
終わりに
Demand やrequest以外にも現実にはまだ起こっていないことを表す接続詞(for fear thatなど)でも出てきます。ぜひ覚えておきましょう!
お読みいただきありがとうございました!
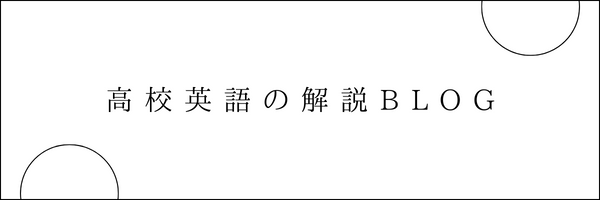
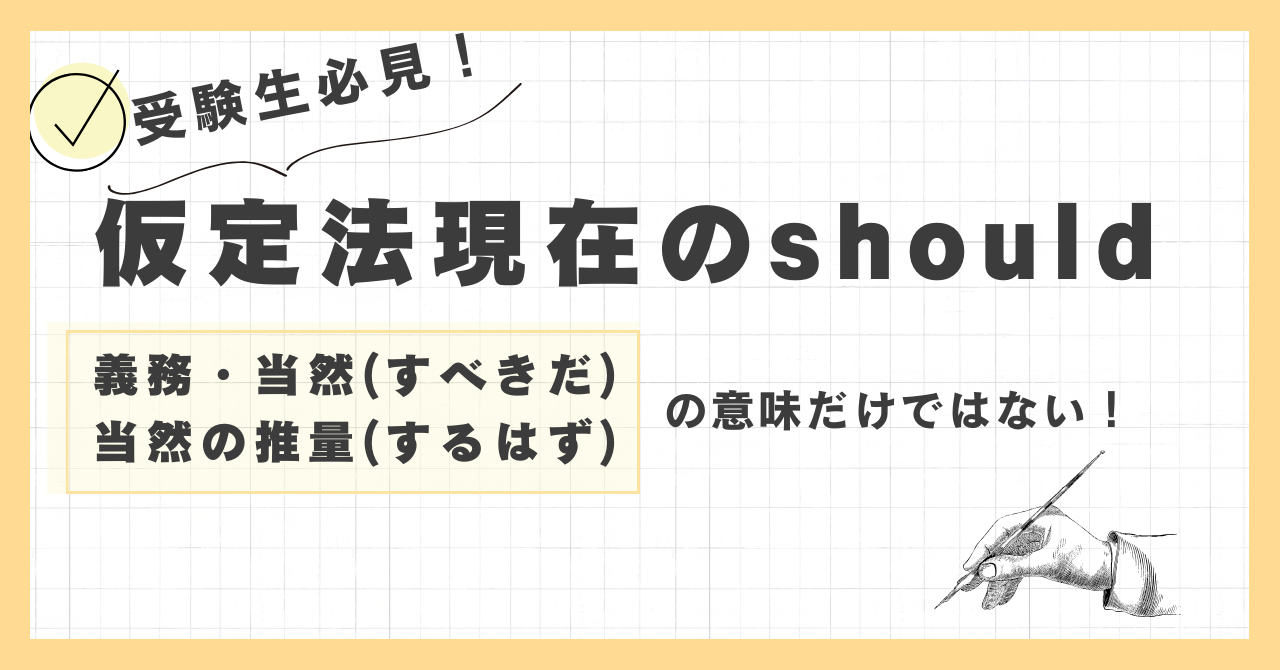
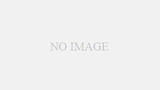

コメント